『書燈』 No.22(1999.4.1)
思い出の一冊
行政社会学部 雨森 勇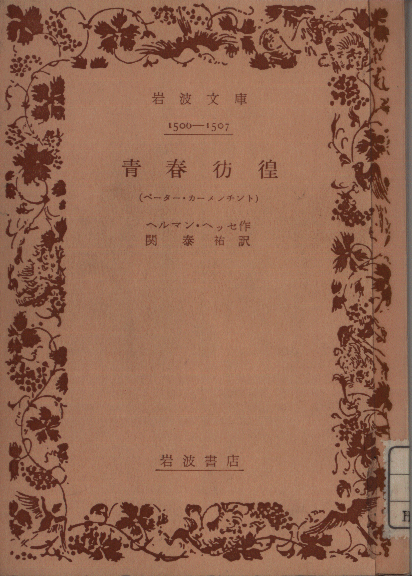
あの“安保闘争”を迎える60年前後の政治の季節の中で、私は殆ど政治的でもなく、さりとてまったくのノンポリというのでもなく、中途半端な文学かぶれの青少年期を過ごした。翻訳物中心に読み漁り読みかじった断片を口いっぱいに頬張り、同人誌仲間が集う茶店(サテン)に毎日のように出かけては相手かまわずやぶれかぶれに吐き出した。といえば、活気に充ちた情景にも見えるが、そこはやはり大学でもネクラの部分を請け負う若者としてのたしなみと誇りを絶えず自覚する場面でもあった。
つまりは、鼻持ちならぬガキの一人だったわけだが、その読書遍歴はわりとまっとうに辿られたのではないかと思う。なぜなら、私もその頃の世代によくあるように、それこそヘルマン・ヘッセを通して海外文学やら哲学に足を踏み入れ、ヘミングウェイ、カミュ、カフカ、ドストエフスキー、サルトル、ニーチェ、ハイデッガー、ヘンリー・ミラーなどなど、殆ど一貫性のない乱読へと誘われたからである。
そこで思い出の1冊となれば、やはり少年期も盛りの高校1年の夏休み、ふと手にしたヘルマン・ヘッセの『青春彷徨』(岩波文庫)をあげるしかない。出会いとは正しくこういう瞬間を指すのだと思えるほどに、私はこの1冊に魂を抜かれたのである。中学時代で日本文学は卒業したと勝手に思い上がっていたふしもあるが、翻訳物独特の重層的な文体、形容詞・副詞が華麗に連なり、間接詞がとどまることを知らない文章の、それまで味わったことのないコクというやつにすっかり殺(や)られたといっていい。
翻訳物に慣れたいまの人たちには、この驚きは分からないだろうと思う。ましてや田園風景の刻明な描写でこれでもかと迫るヘッセときたら!間を置かず放課後ともなれば武蔵野をさまよい歩く少年となった私であるが、やたら美文調の文章を書くようにもなり、それが一度ならず学校新聞の一隅を飾ることにもなって、小説家になりたいなどと他愛もなく憧れた。受験にも失敗し、長ずる前に夢は消えてもなお、田園をさまよう癖だけは残り、この福島にきてなにが一番うれしいかといえば、雪を覆った美しい山々を見ながらあてもなく歩けることだと明言できる。
gakujo@lib.fukushima-u.ac.jp